普通免許を取得された人を前提とした上で、トラックドライバーに興味がある人に、ドラ歴20年の経験者が、運転免許の種類について解説します。免許制度を理解し、あなたが希望するトラックの免許を取得しましょう。
運転免許制度と免許の種類について
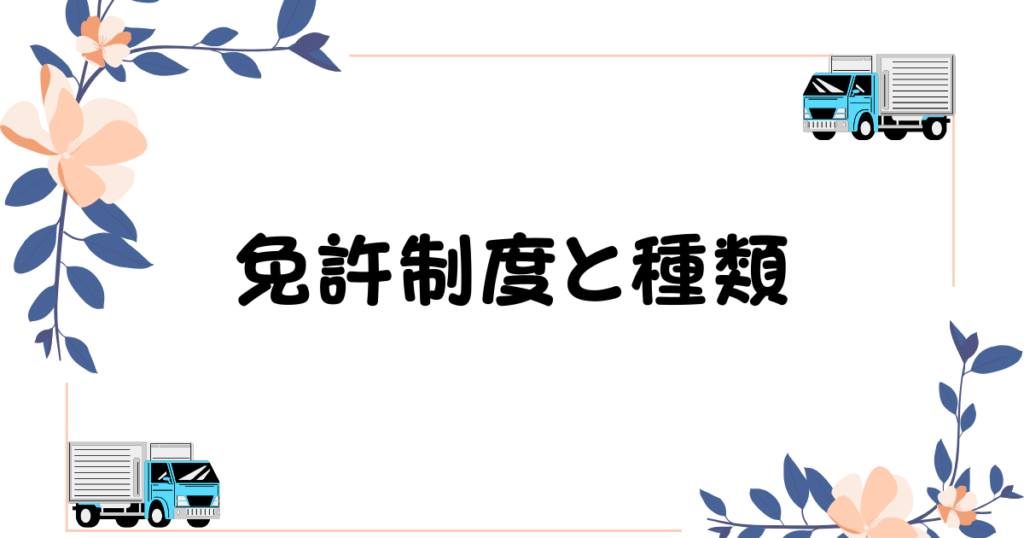
免許制度は今日まで、3回改正されました。あなたが普通免許を取得した年月日により、運転できる車両が変わるので注意が必要です。
以下に運転免許の改正について、詳しく解説します。
①2007年(平成19年)6月1日以前に取得
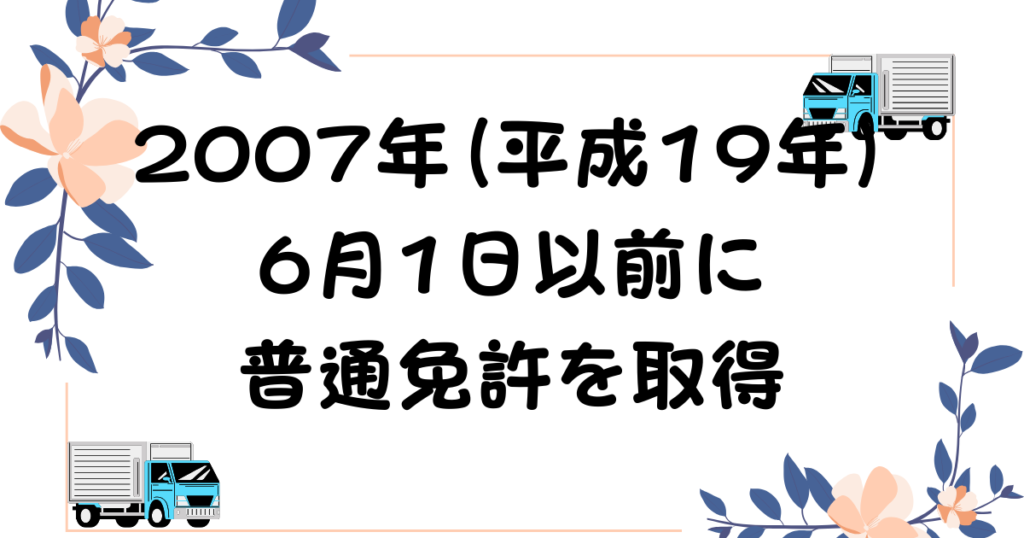
| 年齢 | 普通免許保有歴 | 車両総重量 | 最大積載量 | 運転できるトラック | |
| 普通免許 | 18歳以上 | なし | 8トン未満 | 5トン未満 | ワゴン・2・4トン車 |
| 大型免許 | 20歳以上 | 2年以上 | 8トン超 | 5トン超 | 10トン車 |
免許区分が普通免許と大型免許の2種類しかなく、普通免許を持っていれば4トン車まで運転できる時代。平成19年6月1日以前に普通免許を取得していれば、運送業界への転職は有利と言えたでしょう。しかし、普通免許があっても、トラックの運転経験がないので、車両感覚になれることから始めてみてはどうでしょうか。
運送会社に入社した当時、わたしは普通免許を取得しており、4トン車まで乗れる時代でした。未経験スタートで、2トン車から運転しました。運転に慣れたころ会社からの勧めで、4トン車にも乗るようになり、気づけば仕事の幅を広げることになりました。
運転免許があるとはいえ、実際にトラックに乗り車両感覚がわかるまで、1〜2週間かかります。普通免許があれば4トン車まで乗れるからと軽く考えていると、先輩ドライバーに注意されるでしょう。乗用車感覚で運転すると、大事故につながる恐れがあるからです。乗用車に比べトラックは車両自体が大きいので、ハンドルを大きく捌く技術がなければ、電柱や縁石に接触しかねません。ハンドルをどれだけ切れば、車体はどう動くのかを身体で覚えるのが重要です。とはいえ、平成19年6月1日以前に普通免許を取得していれば、中型トラックまで運転できるので、人手不足の運送業界には有利に働くでしょう。
②2007年(平成19年)6月2日~2017年(平成29年)3月11日に取得
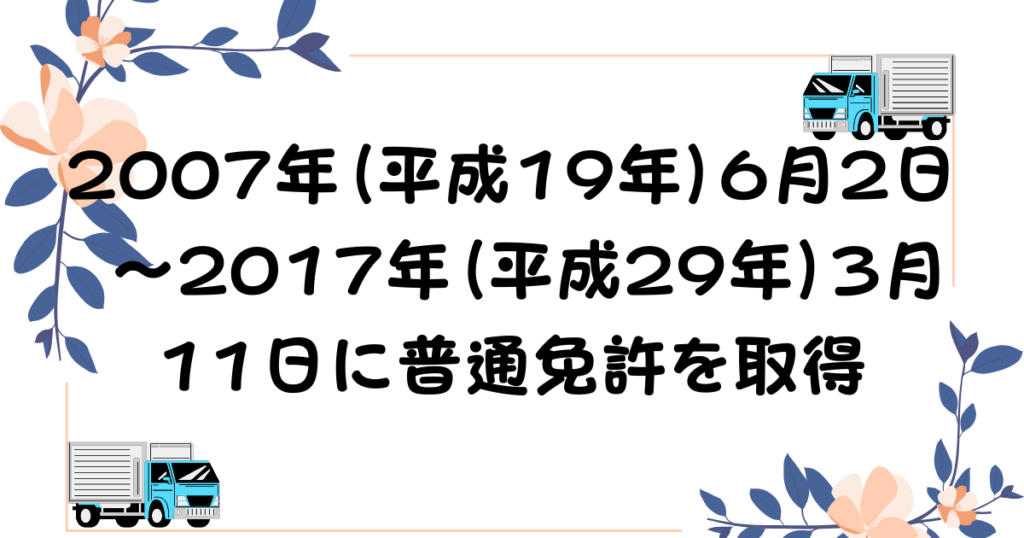
| 年齢 | 普通免許保有歴 | 車両総重量 | 最大積載量 | 運転できるトラック | |
| 普通免許 | 18歳以上 | なし | 5トン未満 | 3トン未満 | ワゴン・2トン車 |
| 中型免許 | 20歳以上 | 2年以上 | 5トン超11トン未満 | 3トン超6.5トン未満 | 4トン車 |
| 大型免許 | 21歳以上 | 3年以上 | 11トン超 | 6.5トン超 | 10トン車 |
2007年(平成19年)6月2日から免許改正がありました。2007年(平成19年)6月1日までの制度では、普通免許で運転できるトラックの種類が広い点。普通免許さえあれば4トントラックを運転しても良いのです。運送会社はトラックの運転講習などをする余裕もなく、経験不足から交通事故を多発させる原因となり、中型免許が新設されたのでしょう。
上記の表から、普通免許を取得して2年以上経過しなければ、中型免許を受講する資格が得られないのです。
実際わたしがはじめてトラックに乗車したとき、車両の長さ・幅・高さなど、乗用車では感じられない恐怖がありました。しかし、「わたしはドライバーで生計を立てる」と決めてから、トラックの運転に慣れるため、先輩を助手席に乗せ、右左折・バック・切り返しを徹底的に教えてもらいました。トラックの運転は技術職。身体にしみこませて覚えるものであり、頭で理解するものではありません。
1年経つころにはトラックにも慣れますが、同時に事故も起こしやすい時期です。例えば、運転できる慢心からの事故。「一時停止だが車の通りが少ないから行けるだろう」とか、「信号が黄色に変わったけど渡れるだろう」と勝手に解釈した結果、衝突する羽目に。
語弊があるかもしれませんが、「事故も経験のうち」と思っています。事故の経験がない人が、万が一事故に巻き込まれた場合、運転の恐怖心から立ち直るまで時間がかかるからです。
ドライバー歴20年以上で事故の経験がない人は、滅多にいないでしょう。無事故が一番良いのはわかります。わたしも大小問わず事故の経験をしましたが、人に励まされたおかげで、今も現役を続けています。仕事は失敗を改善して学ぶもの。特にトラックドライバーは、走る凶器にもなりますから、まわりの人に勇気づけられる環境があると、続けられる仕事になるのでしょう。
③2017年(平成29年)3月12日以降に取得
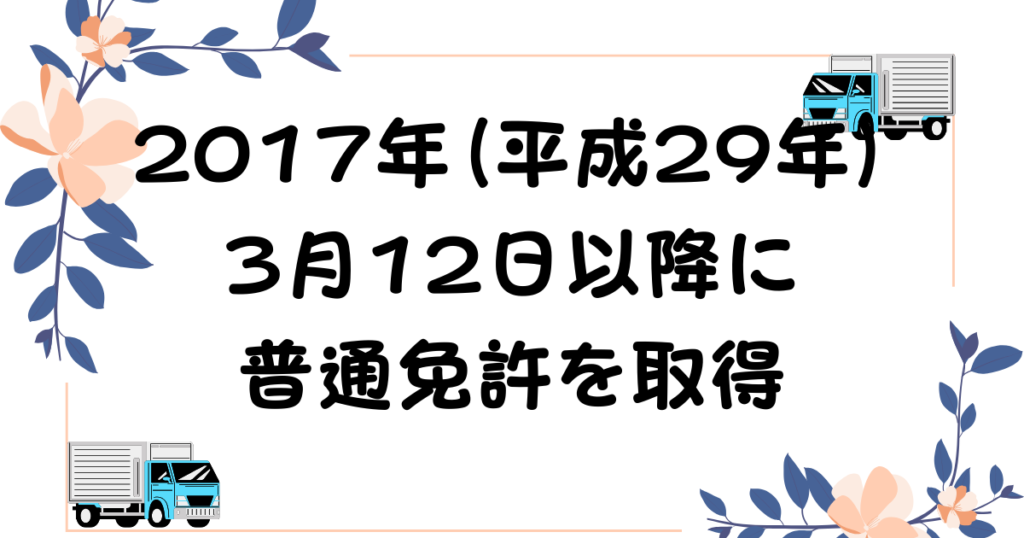
| 年齢 | 普通免許保有歴 | 車両総重量 | 最大積載量 | 運転できるトラック | |
| 普通免許 | 18歳以上 | なし | 3.5トン未満 | 2トン未満 | ワゴン・軽トラ・1トン車 |
| 準中型免許 | 18歳以上 | なし | 7.5トン未満 | 4.5トン未満 | 2トン車 |
| 中型免許 | 20歳以上 | 2年以上 | 11トン未満 | 6.5トン未満 | 4トン車 |
| 大型免許 | 21歳以上 | 3年以上 | 11トン超 | 6.5トン超 | 10トン車 |
準中型免許 > ふたば自動車学校 (futaba-ds.com) ふたば自動車学校より
2017年(平成29年)3月12日より準中型免許が新設されました。普通免許で運転できる車両を限定し、交通事故を減らすのが目的。段階的に準中型免許、中型免許とステップアップし、車両感覚になれるためでもあります。しかし、運送業界は慢性的な人手不足で、免許を取得し即戦力になるまで時間がかかり、免許費用も安くはありません。
トラックドライバーになりたいなら、長期スパンで経験を積む覚悟を持ち、会社側は、社員を育てる気持ちで接する必要があります。
わたしの場合、運送会社が受注した仕事が、大型免許のいる仕事でした。必要に迫られて大型免許を取得したようなもの。現状に不満があるわけでもなく、白羽の矢が立ったのが、たまたま自分だったのです。とはいえ、大型をとってしまえばどんなトラックも乗れるので、転職の強みにもなります。
車両が大きくなるほど、事故による損害は莫大。街中や人通りが多い交差点など、あらゆる方向に神経を使い運転する必要があります。車両の大きさにより使う用途は変わるので、大型トラックだと長距離メインで走る仕事が多いです。車両が大きくなると、交通量や人気が少ない時間帯を問わず、人や建物に注意し続ける緊張感はあります。
受験資格特例教習
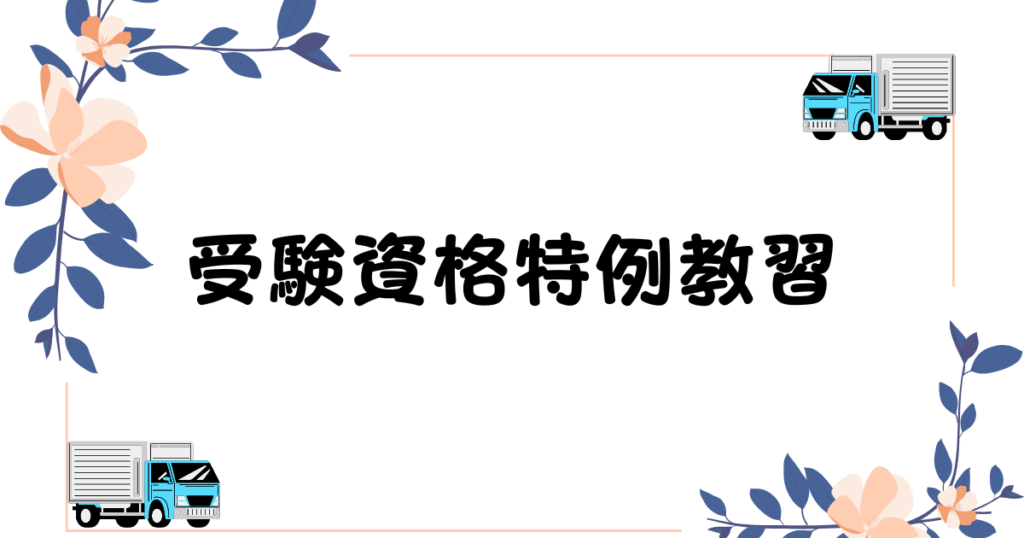
通常、大型免許は21歳以上で免許歴3年以上、中型免許は20歳以上で免許歴2年以上となりますが、令和4年(西暦2022年)5月13日以降、「受験資格特例教習」を受講すれば、年齢19歳以上で免許歴1年以上に引き下げられます。
特例で免許を取得した場合、大型は21歳・中型は20歳までの期間に3点以上の違反をした場合、「若年運転者講習(連続2日間で合計9時間)」を受けなければなりません。講習を無視すると、運転免許が取り消されますので、運転資格である年齢に達するまでは、特に安全運転を心がける必要があります。
13tokureikyoushu.pdf (wakayama.lg.jp) 和歌山県警察本部交通部運転免許課 講習・教習所係より
jyakunenkikanseido.pdf (pref.toyama.jp) 富山県警察本部 運転免許センター より受験資格特例教習について解説|合宿免許なら免許の匠 (menkyo-takumi.com) 免許の匠より
車両総重量と最大積載量の違い
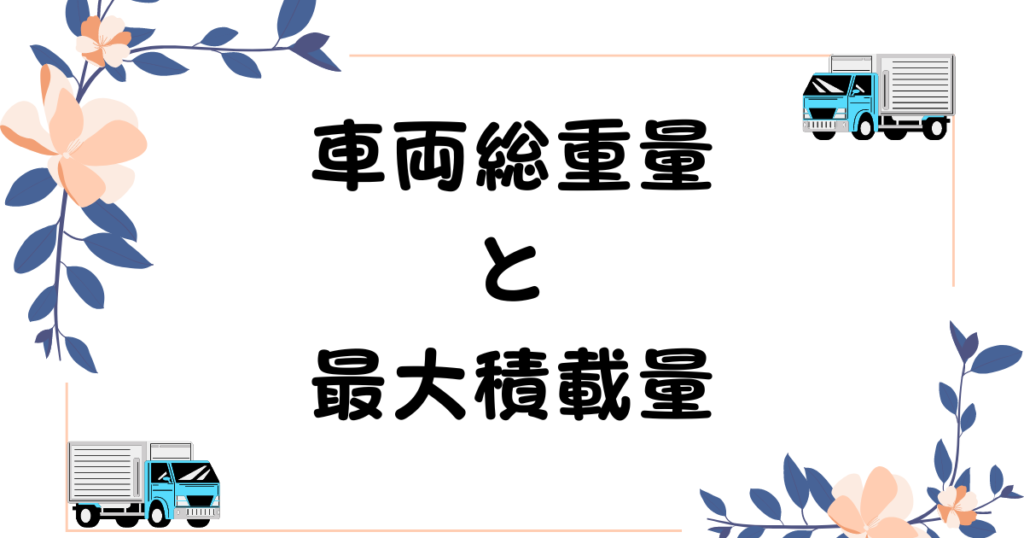
トラックに乗務するようになると、荷物の重量も考えるため、車両総重量や最大積載量を理解しておくとよいでしょう。車両総重量と最大積載量の違いについて、簡単に解説します。
車両総重量
車両総重量とは、車両自体の重量に加え、乗車定員の体重(1人55kgで計算)に最大積載量を合計した重さです。
車両重量は、「直ちに動ける状態」を指し、オイル・冷却水・ウォッシャー液・燃料などが満タン状態である重さです。
最大積載量
最大積載量とは、積める荷物の最大重量です。
最大重量は車検証に記載されており、安全に運べる荷物の限界値の意味。誤解してはいけないのが、4トン車だから4トン分の荷物が積めるわけではないのです。冷凍車や冷蔵車など車両の重量が増えると、積載の限界値は小さくなり、最大積載量が変わるので気をつけましょう。
準中型・中型・大型免許の費用
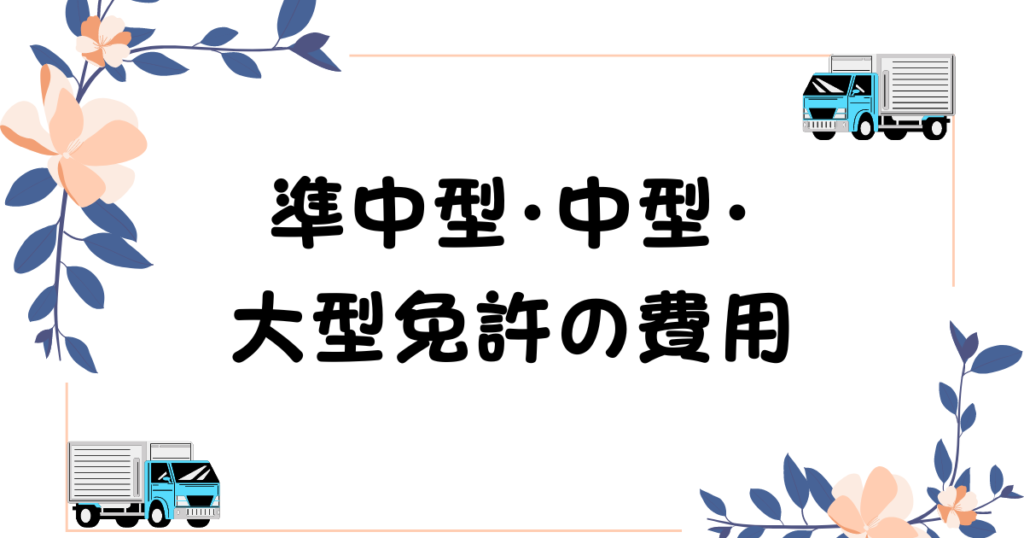
普通免許を取得している前提で、2017年(平成29年)3月12日以降に、準中型免許から段階的に取得する場合の費用を解説します。
仮に、20代男性が準中型免許を取り、実務経験を経て中型・大型免許を取得するまでの免許費用について解説。あくまで目安なので、参考としてください。
準中型免許費用(普通免許を所持している場合)
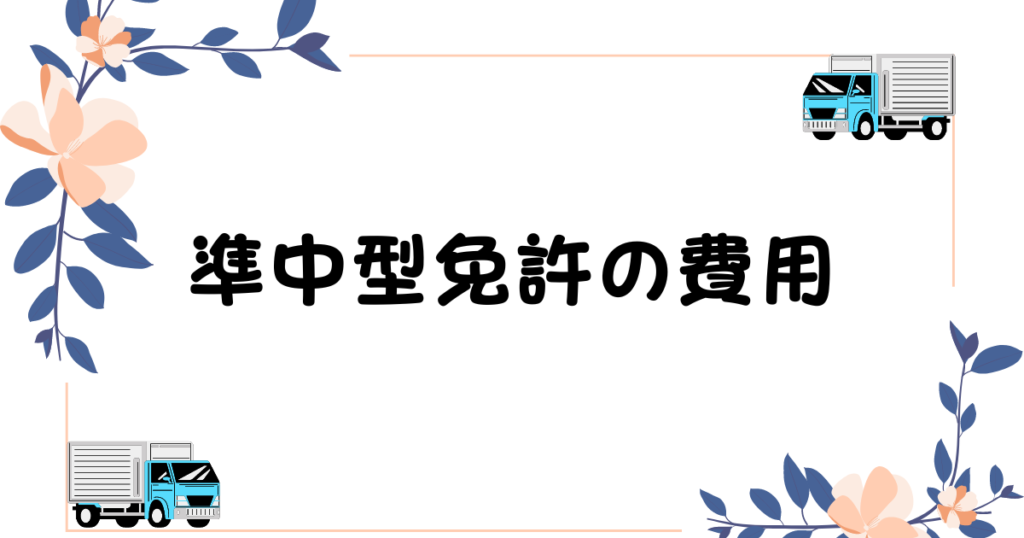
| 現在所持している免許 | 免許取得費用(税込み) |
| 普通免許(マニュアル) | 159,170円 |
| 普通免許(オートマ) | 187,330円 |
| 仮免許試験手数料など | 3,520円(非課税) |
中型免許費用(準中型を所持している場合)
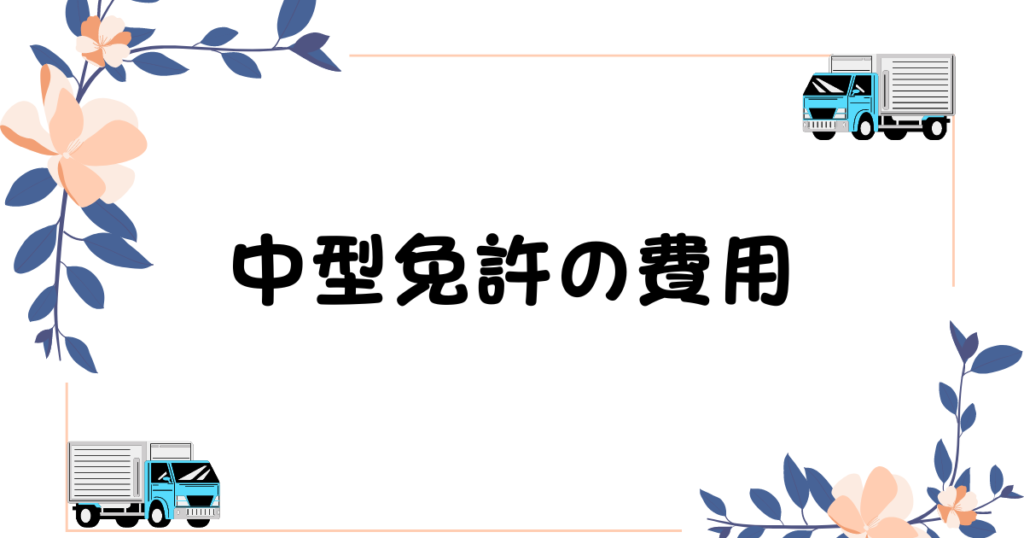
| 現在所持している免許 | 免許取得費用(税込み) |
| 準中型免許 | 142,670円 |
| 仮免許試験手数料など | 2,850円(非課税) |
大型免許費用(中型免許を所持している場合)
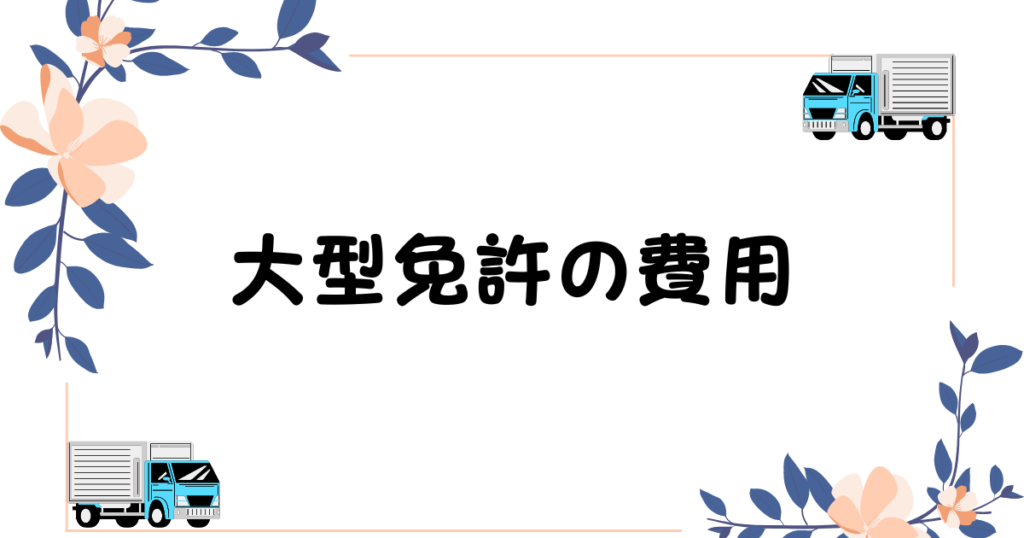
| 現在所持している免許 | 免許取得費用(税込み) |
| 中型免許 | 288,090円 |
| 仮免許試験手数料など | 2,850円(非課税) |
上記の事例は、普通免許を持っている前提で、準中型免許から段階的に取得する場合を想定した免許費用の目安です。普通免許の取得年月日により、運転資格の有無が変わるため、より詳しく知りたい人は、下記のサイトを確認してください。
教習料金・各コースのご案内 | 中央バス自動車学校|全車種技能試験免除校 (chuo-bus.co.jp) 中央バス自動車学校より
会社が免許費用を負担するメリットと注意点
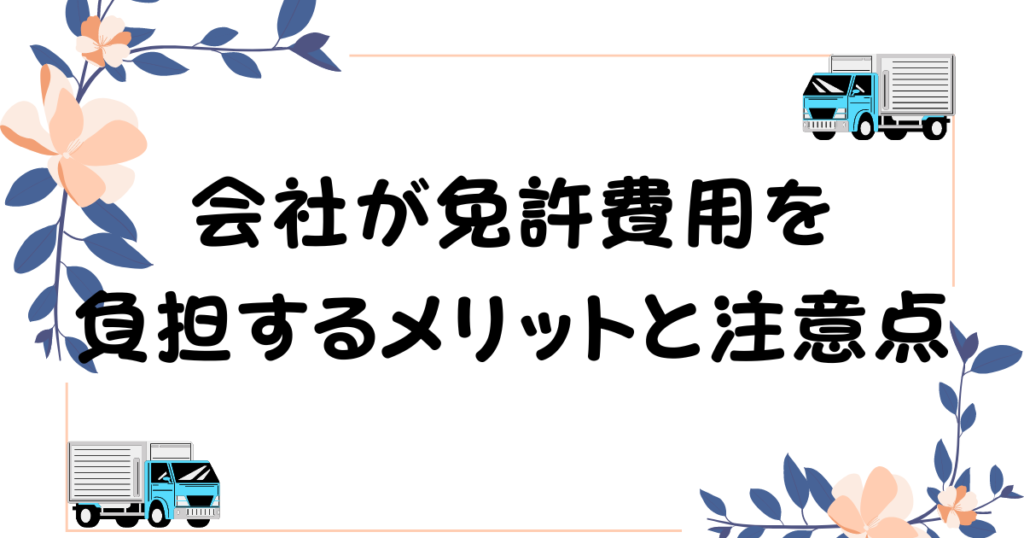
中型トラックは運送業界で最も活躍する車両です。トラックドライバーを目指すなら、中型免許まで取得したいところ。気になる免許費用ですが、負担してくれる運送会社もありますので、メリットはぜひ活用しましょう。ただし、注意点もありますのでご確認を。
メリット
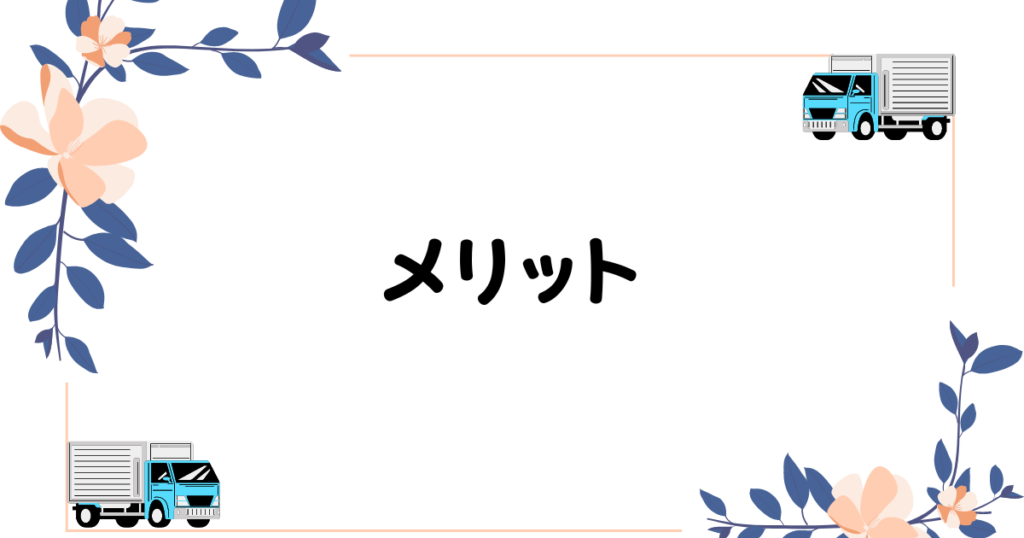
費用負担の軽減
準中型や中型免許を取得するにも、金額は安くありません。会社が費用を負担してくれるのは、トラックドライバーの免許を取得したい人には大きなメリットです。
例えば、普通免許しか取得していない人がトラックドライバーを目指す場合、中型免許を取得してから転職活動をしようと考えがちですが、運送会社が決まらなければ仕事ができません。未経験で不安要素も多いでしょうが、職場を先に決めるのが重要です。免許があっても、実際に仕事をしてみないと、ドライバーが続けられるかは別問題。仕事の流れを理解して、頑張れそうと思えるなら、会社に費用を負担してもらいましょう。
仕事の幅が広がる
大型免許を取得すれば、仕事の幅が広がります。納品物が多い店舗や取引先では、中型トラックでは積載オーバーになるため、大型トラックでなければ輸送できません。大型免許を持っていれば、トレーラー車以外すべてのトラックに乗れるので、走れるコースも増加。資格手当もつくので、給料面でもメリットがあります。
注意点
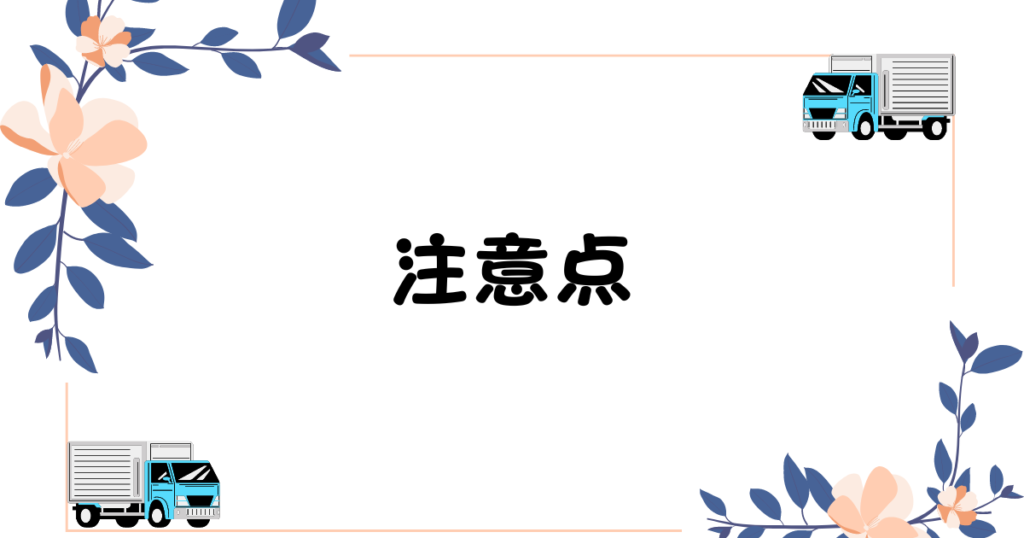
免許費用の請求
会社が高額な免許代を負担する一方で、1年に満たず退職した場合、免許費用を請求される可能性があります。会社はドライバーとして活躍してくれることを期待しているので、短期間で退職されると、費用を負担した意味がなくなります。退職を防ぐため免許取得から3年とか、5年と在職期間を決めるのは、会社に貢献したとみなすために設定しているのでしょう。
運送会社は免許センターではありませんので、「3年いれば返金しなくてよい」などと考えず、採用された会社で長く働けるよう頑張るのが賢明です。
転職のリスク
運送会社は慢性的に人手不足で、免許費用を負担することで転職される恐れがあります。
例えば、求人文句を「未経験歓迎、入社後免許取得が可能」と謳えば、入社する人が増えるかも知れません。しかし、免許取得後の在籍年数を満たせば、より条件の良い運送会社へ転職される危険性をはらんでいます。
例えば、下記の条件だと気持ちが動くことも。
- 自分の希望するコースが選べる
- 給料・手当・休日などが今の会社より充実している
- 安全対策や社員教育が徹底され、長期的に安心して働ける
少しでも条件が良いと人は心動かされるもの。働いて稼ぐ金額が増えれば、生活に余裕が生まれます。免許費用を負担してくれた恩はあれど、環境の整った会社に転職することで今より優遇されるのであれば、引き留めるのは困難。給料のベースアップや会社の貢献度に応じた役職を開示するなど、社員の離職を防ぐための企業努力は必要となるでしょう。
経験者からひと言
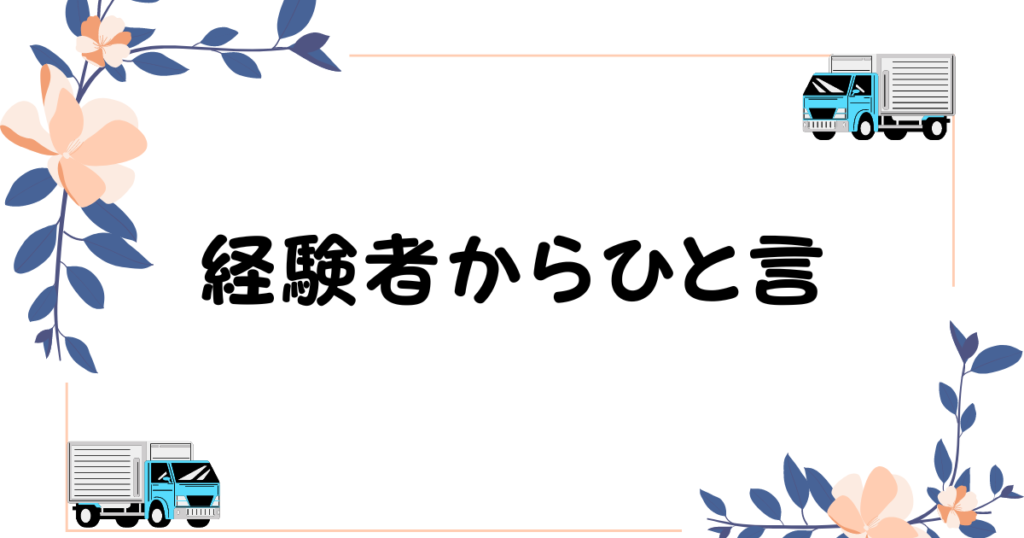
トラックドライバーに必要な運転免許について解説しましたが、取得した年月日により、運転できる車両が変わります。免許制度が変わった背景は、普通免許で中型トラックを運転できるため、事故が多発したからでしょう。
これから中型や大型の免許を取得する人は、段階を踏む必要があるので、面倒くさいかもしれません。しかし、少しの油断で大きな事故につながるトラック。時間をかけて、トラックの運転に慣れていきましょう。トラックドライバーは、経験を重ねた分、運転技術は向上します。
免許証は一度取得すれば一生残りますから、交通事故で免許証に事故歴が残らないよう、十分注意して運転しましょう。トラックの特性を知り運転経験を積んで、見本となるトラックドライバーを目指しませんか。











